- スリーパー効果って何?
- 見込み客に確実に信用される方法を知りたい
- 成約率を今より格段に高めたい
コンビニの雑誌コーナーで、ゴシップ雑誌の表紙の見出しをみると、つい手に取ってパラパラとめくってしまうケントです。
(こらっ、伸びるな僕の手!それが目的ではないだろうがっ(;´・ω・))
ただ、ゴシップ記事は確かに好きなのですが、その一方で、どこかしら「どうせ嘘でしょ?」と少し疑った目でみてしまう自分もいます。
ですが、その後もワイドショーなどで何度も報道され同じような映像を何回も見ていると、次第に「もしかして本当なのかな・・?」と思ってしまいます。
これってけっこうありますよね?
たとえば、日常生活のウワサ話もそうです。
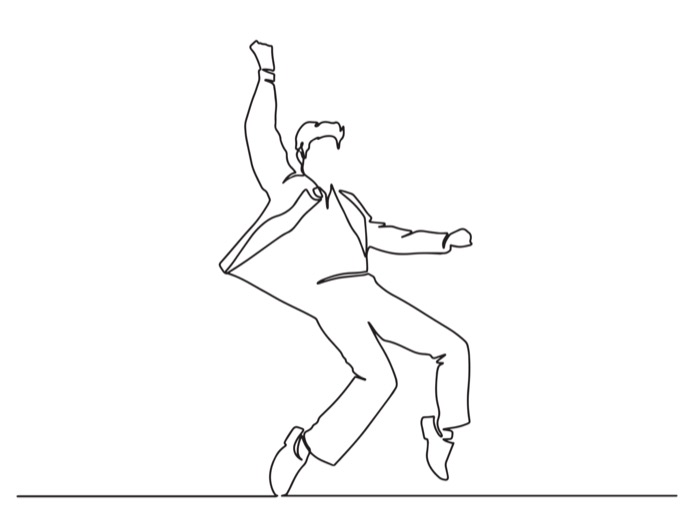
「あの仕事がデキる部長の頭・・・植毛らしいよ?」



「えー、またまたぁ・・」
ある人からそんな信じられないウワサを聞いても初めは信じてなかったのに、
後日、別の身近な仲の良い同僚からも同じことを言われたら、



「あの仕事がデキる部長の頭・・・植毛らしいよ?」」
いつの間にか信じて、当たり前のように自分も同じこと他の人に言ってた、なんてこともありますよね?(汗)
この現象はちゃんと人間心理に基づいていて、こういう時の状況を「スリーパー効果」って言います。
信頼性の低い情報源から得た情報であっても、時間がたつと信頼性が低いということを忘れ、その情報を信じてしまうという現象
アメリカの心理学者、カール・ホブランドさんが提唱したものです。
人間は時間が経つと、情報の信頼だけが増して記憶に残ってしまうんです。
信頼性の低さを”忘れる”=(眠る) という語源で「スリーパー効果」と呼ばれているんですね。
例えば、信頼する友人Aさんから「この商品めっちゃいいらしいよ!」と勧められたら 、
「Aさんがいうなら買ってみようかな」と思ってしまいます。
その情報源がどこから来たのか分からないのですが、信頼できるAさんが言っているのだからなんとなく信用してしまいます。
逆にあまり親しくないBさんから同じ商品を勧められたとしても 「本当に?適当なこと言ってるかも・・」となかなか信用することはできないですよね。
ただ、結局はBさんもやはり信用してしまうかもしれません。
その理由は、スリーパー効果がはたらき、時間が経過すると、情報源の信用度の記憶が薄れ、「情報の内容」のみの記憶が残るからですね。
このスリーパー効果を式に表してみると・・・
情報を得た時点での信用度
(Aさんの信用度)10 + (情報の内容の信用度)5 = 10
(Bさんの信用度)1 + (情報の内容の信用度)5 =1
このように、初めは情報の内容より誰が言ったかが重要視されます。
ですが、時間が経つと・・・
時間経過後の信用度
(Aさんの信用度)10 + (情報の内容の信用度)5 = 5
(Bさんの信用度)1 + (情報の内容の信用度)5 = 5
という結果になるのです。
時間が経てば、誰が言ったかその記憶は薄れ、最終的に信用において重要視されるのは「情報源」よりも 「情報の内容」ということになるんですね。
そして、Bさんから得た情報も、他のところで同じ話をたまたま耳にすると,
「え?あの話って実は本当かも・・」
といつの間にか信じているのです。
逆に信頼するAさんの情報に対しては時間が経つと,
「あれって信じていいのかな?」
なんて少し疑ってしまうようになります。
つまり、「スリーパー効果」とは、時間が経つことで初めは疑っていた情報でも、多方面から同じ情報が入ると、結果的に信じてしまう心理作用のことです。
・・・って言われても、さっぱり分からないですよね(む・・むずかしい・・・)
では、わかりやすく例をだしてみますね。
けっこう世の中を大きく動かすほどの事件もよく起こっています。
この「スリーパー効果」をあなどってはいけないことが分かると思います。
スリーパー効果の重要性を具体例でわかりやすく紹介
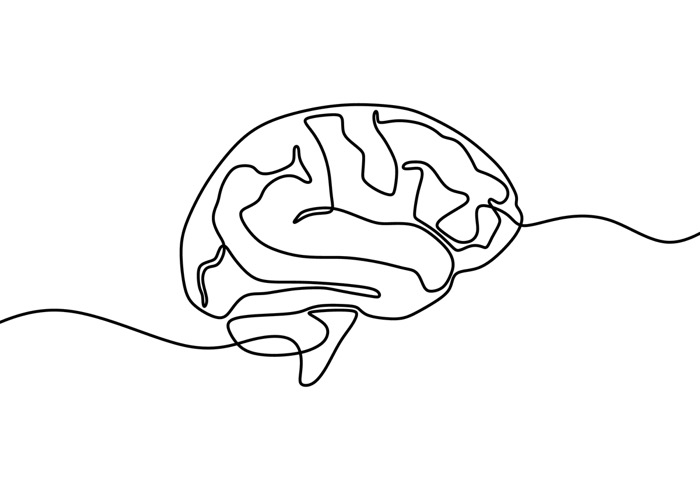
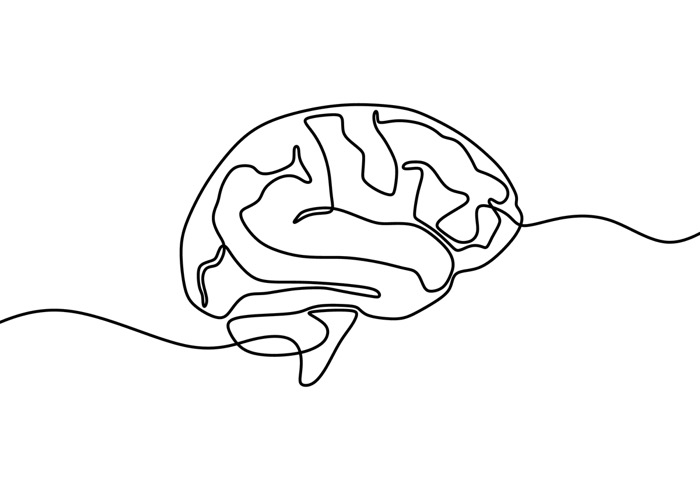
過去の歴史をみても例は本当にたくさんあります。
たとえば有名なものとしては・・・
ネス湖のネッシー
1933年5月にマッケイ夫妻が湖畔ほとりを散歩している時に初めてネッシーが目撃されました。
ただその時は写真でなく、目撃証言だけでしたので信ぴょう性にかけ話題にはなりませんでした。
ですが、同年の11月に状況が一変します。
ヒュー・グレイ氏によって、史上初のネッシー写真が撮影されたのです。
彼は、ネッシーの写真を撮ろうと湖畔を歩いているときに偶然に遭遇し撮影に成功したということでした。
ただ、その写真はピンボケで、何かが泳いでいるようには見えますが、そこがネス湖であるかどうかですら判別できないものだったそうです。
ですが、立て続けに耳に入ってきたこの情報に、世間は「ネス湖のネッシー」に少しずつ関心を寄せ始めます。
そして、翌年1934年4月に世界的にも有名なあの写真がついに公表されました。


「外科医の写真」です。
社会的信用のある医師のロバート・ケネス・ウイルソン氏が撮影したもので、この写真がイギリスのタブロイド紙「デイリー・メール」に持ち込まれ掲載されたのです。
ちなみに「デイリー・メール」は、世界中で読まれるほど読者が多く、影響力の高い新聞です。
これをきっかけとして世界中に瞬く間に「ネス湖のネッシー」情報が拡散し、話題騒然となっていったのです。
この年を「ネッシー元年」と言い、これを境に様々な目撃情報が生まれることになります。(なぜか不思議とどんどん目撃され始めるんです(笑))
そこからは、あらゆる人々がネス湖のネッシーの存在を証明するために莫大な費用をかけて探索することになります。
たとえば探索者としては、著名な博物学者、ボストン応用科学アカデミー研究チームなどが名乗りを挙げました。
そしてなんと、当時参議院議員だった石原慎太郎さん率いる「国際ネッシー探検隊」も7週間2億円の時間と費用をかけて探索しているんですね。(石原さんも若かりし頃は色々されているんですね!)
ですが、本当に多くの人が探索するも結果は実らず、真相解明は先送りになるばかりでした。
そんな長年に渡り、世界中の人々を熱狂させてきたネス湖のネッシーですが、1993年11月にとんでもない報道が流れます。
「外科医の写真」は捏造
真相は以下の通りです。(以下箇条書きでまとめます)
・クリスチャン・スパーリング氏が捏造と死ぬ間際に告白
・彼の養父が当時の首謀者
・養父は知り合いの外科医(ロバート・ケネス・ウイルソン氏)に写真公表を依頼
・依頼した理由は社会的に権威性のある人の方が信用されると思ったから
・ただ実は外科医でなく産婦人科医だった(信用度は外科医の方が高いと思った)
・「外科医の写真」としてタブロイド紙に持ち込み世界中に広まることに
・予想外の社会現象に戸惑い、本当の事が言えなくなる
・約60年あらゆる人がネス湖のネッシーに熱狂し、多くの人が目撃
1934年の「外科医の写真」に始まったこの騒動ですが、捏造が公表された後でもその熱は収まらず最近では2016年にもネッシーの写真が公表されたそうです。
捏造が発覚してもなお信じている人もいるんですね。(もはや人類のロマンです(笑))
ネス湖のネッシーは、あらゆる人の証言や情報誌により世界的な観光名所となり、大きなお金が動くこととなりました。
この世紀の珍事は、「スリーパー効果」と深く関わっているんです。
実は同じような展開は日本でも過去に起こっており、大きな騒動になったことがあります。
豊川信用金庫事件


この事件は昭和48年に起きた「豊川信用金庫事件」と言って、普通の女子高生の何気ない発言が、ひとつの銀行を潰してしまうような騒動になった実話です。
その女子高生は、豊川信用金庫に内定をもらい、仲の良い友達に「私、あそこの銀行に就職することになったの」と話したそうです。
するとそれを聞いた友人が「銀行は危ないって。銀行強盗に襲われたらどうする?将来性もないと思う」と少し冗談っぽく言ったのですが、この会話がのちに騒動へと発展します。
この友人の言葉を聞き、不安になった彼女は帰宅後に「あそこって危ないの?」と親に聞きました。
すると親はよくわからないので別の知り合いに「銀行って危ないのか?」と尋ねると、なぜか「あの銀行は危ないかも」と認識してしまったのです。
この「危ない」という言葉が予想外に独り歩きしていき、いつからか「豊川信用金庫の”経営状況”が危ないらしい」と話の内容がすり変わっていきました。
そして、その話が人から人へどんどん拡散していったのです。
最初は「いや、あの銀行に限ってそれはないよ」と言っていた人までも、あらゆる方面から同じウワサを聞くとさすがに信じてしまいますよね・・・(汗)
すると、いつの間にか町中の人たちが、
「もうすぐあそこ潰れるらしいよ」
「そりゃ大変だ!はやく預金を下ろさないと」
と信じ込み、豊川信用金庫に殺到したのです。
しまいには、「職員の誰かが勝手に信金の金を使い込んだらしい」「理事長が責任を感じて自殺したらしい」といった悪質なデマまで流れはじめ、パニック状態に。
豊川信用金庫は訳が分からないまま、その時殺到した預金者から一気に引き出されたお金はなんと26億円!
その後は日銀が介入したり、理事長が窓口で顧客対応することで事態は収束したそうですが、デマで存続が危ぶまれるような騒動を起こされたら、銀行としてはたまったもんじゃないですよね(汗)
ちなみに、豊川信用金庫は今も健在で、変わらず営業を続けています。(よかったよかった(*´ω`))
実は日本で割とよく起こっている「スリーパー効果」


この「豊川信用金庫事件」は伝言ゲームみたいにどんどん形を変えながら、人から人へ拡散していき騒動に発展していきました。
たとえば、ちょうどこの事件の6年後に起こった「オイルショック事件」もそうですね。
あれも石油の値段が上がるという噂が形を変え、
「街からトイレットペーパーがなくなる!」
という根拠のないデマによりドラッグストアやスーパーに主婦たちが殺到した騒動です。
このように過去の歴史からみても人間は時間が経つと、
たとえ信頼性の低い情報源から得た情報であってもいろんな方面から耳にするとその情報を信じてしまう傾向にあることが分かります。
ここで読者様にお伝えしたいことは、この「スリーパー効果」を情報発信ビジネスでうまく利用すれば、人の心を動かし、行動を起こさせることができるということです。
行動心理の観点からオススメのアプローチ方法については、プロスペクト理論とは?日常生活を例にして人間の心理を分かりやすく解説で紹介しています。
スリーパー効果は情報発信ビジネスに応用できる
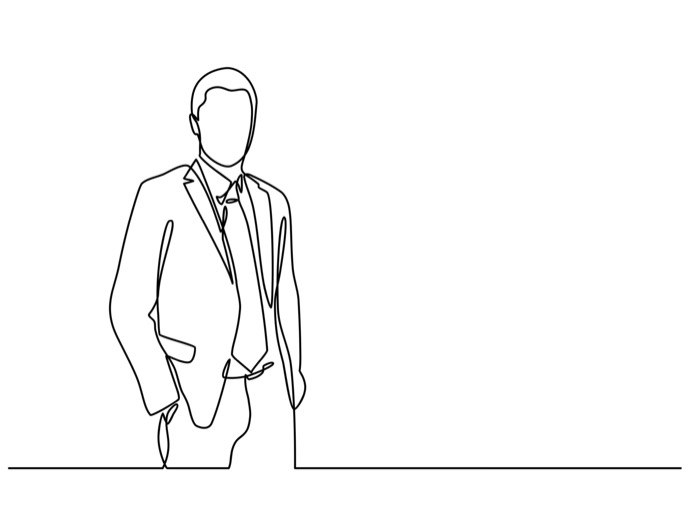
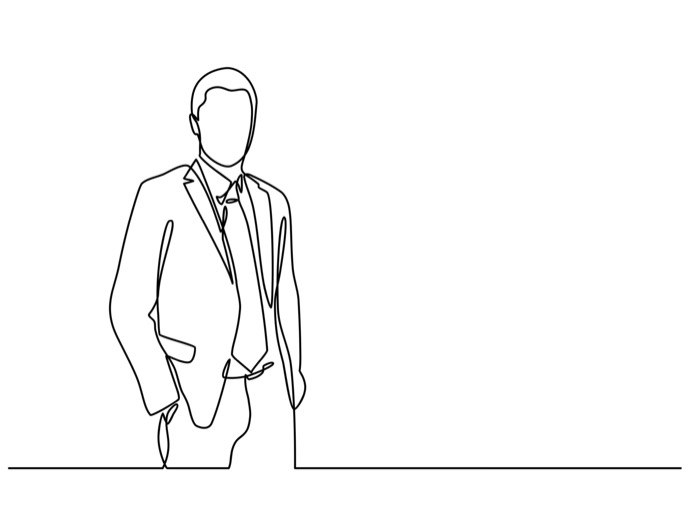
初めは疑っていた情報でも、時間が経ち多方面から同じ情報が入ると、結果的に信じてしまうのが「スリーパー効果」です。
たしかに最初は相手にされなかったネス湖のネッシーの目撃情報も、
同じ目撃情報が続くと人々は「本当かも・・・」と信じてしまったという良い具体例だと思います。
結果として、「自分も目撃したい!」と思い、実際にネス湖に観光がてら大勢の人が足を運んだり、
何億円もかけて探索したりするようにさえなるんです。(つまり多くの証言を戦略的に利用することで莫大なお金が動いているんです)
この人の行動習性は「情報発信ビジネス」においてもすごく参考になると思います。
たとえば、「情報発信ビジネス」ではコンサルティングサービスを商品として売る方が多いです。
大体の人は「自分はこんな実績あるし、このコンサルサービスは〇〇が優れているのでおススメです!」と自分の商品の情報を見込み客に提供し、アピールしますよね。
ですが、見込み客は別に親しくもない情報発信者に初めは「本当に?うそだろ」と疑ってかかります。
そこで、この見込み客の心の壁を突破するテクニックとしてよく使われているのが「購入者の声」です。
ユーチューブなどで「実績者対談」動画を流しているのはよく見かけると思います。
第3者の声を登場させると、相手は「こんなにもうまくいっている人がいるんだ。本当かも・・」と「スリーパー効果」が働くのです。
これはつまり、いろんな人達が証言することで、賛同者(目撃者)が増えていったネス湖のネッシーのパターンと同じです。
ただし、それだけじゃまだ足りません。
そこで、さらに「推薦者の声」も紹介します。
業界の実力者、インフルエンサーなど社会的に地位のある人のコメントを入れると、もっと信じやすくなります。
とくに日本人は権威性のある人の発言は敏感に反応してしまうので効果は抜群です。
(年収〇〇のあの人も推薦!・・なんてお金の額を出すと特に日本人は弱いです)
これはネッシーの時でも、社会的信用のある「外科医」や世界的に読まれている「デイリー・メール」を情報提供者として使ったことと同じ効果です。
そして、さいごに「外科医の写真」のように、実績を証明する写真も添えると、見込み客はたちまち商品が欲しくなるんです。
これが恐ろしいのは、実体が分からなくても印象によって人は信じてしまうところにあります。
だから、「情報発信ビジネス」=「詐欺だ」という声も後を絶たないのは、そういった演出がしやすいからですね。(賢明なあなた様なら騙されないと思いますが(*´ω`))
この流れは、「コンサルティング」など情報発信ビジネスだけではありません。
あらゆる分野のビジネスでもパターン化されています。


たとえば、新作映画もそうです。
よく公開直後は、映画に詳しい著名人を使い「これは今まで観たことないほど最高傑作だ!」みたいな口コミ的な発言を雑誌などで載せていますよね。
あれも、初めの情報では発信源が誰かが重要になってくるので「スリーパー効果」を期待したものです。
ただ、これでは「ヤラセだろ」と思う人もいるかもしれません。
そこで、もう一手間加えるんです。
それが、映画を見終わった直後の一般人に対する突撃インタビューですね。
「めちゃくちゃ面白かったです!!」
「感動して泣いちゃいました!」
というコメントや興奮している姿を撮って、CMとしてお茶の間に何度も流します。
そして、「興行収入NO.1!!公開から第〇週目にはやくも○○万人突破!」というインパクトのあるキャッチコピーをCMの最後に添えるんです。
キャッチコピーも超重要なので、情報発信ビジネス|魅力的なキャッチコピーの例と作り方【日常体験ベース】も読んでみてください。
著名人だけではなく一般人の証言もクロスさせて情報を何度も流すことで、「この映画はむちゃくちゃ面白いに違いない!・・・週末行こっかな」となるのです。
ですが、よくよく考えると、突撃インタビューの相手も「一般人」かわかりませんし、なんだかどの映画も「◯◯でNO.1!」と言っているような気がしませんか・・・?(笑)
このように「スリーパー効果」とビジネス(お金を稼ぐこと)は密接に関係しており、ち密に人間の心理に基づいて戦略が練られていることに気付きます。
ゆえに、最初は疑っている人の心をゆっくり溶かし、行動を起こさせることができるのです。
この視点は本当に重要であり、ここをキチンと押さえていなければ、あなたの売上は知らぬ間に取りこぼしをしているかもしれません。
つまり、あなたが自分の商品を売る時でも、決して感覚的に説得するのではなく、
これらの人間の心理に基づく行動習性をきちんと捉えて戦略的に説得していくと、成約率が圧倒的に高まるのです。
(心理学って、ビジネスとめちゃくちゃ密接に関係しますので学ぶ価値はありますよ)
ちなみに、人々を熱狂させる危険な方法も知りたくないですか?【悪用厳禁】グランファルーン・テクニックとは?あなたの見込み客を熱狂させる秘密もチェックしてみてください。
スリーパー効果とは?重要性をわかりやすく紹介【具体例あり】まとめ


お疲れ様でした。
今回は「スリーパー効果」をご紹介しました。
(かんたんに紹介しようと思って書き始めたのですが、自分でも予想外に長文になってしまいました。ここまで約7000文字です(汗))
過去の歴史から紐解いても、多方面から計画的にアプローチすると「スリーパー効果」がはたらき、人は信用してしまう傾向にあります。
これは、情報発信ビジネスにおいてすごく重要な視点だと思います。
ぜひ試してみてくださいね。
この記事が読者様の頭の片隅に少しでも残ることを期待して今回は終わりたいと思います。
ではでは、最後まで読んで下さりありがとうございました。
ケント
流行する仕組みと人間心理の関係性についても、【バンドワゴン効果】鬼滅の刃はなぜ流行したのか?マーケティングでも重要な考え方を紹介でインプットしておいた方が良いと思います。
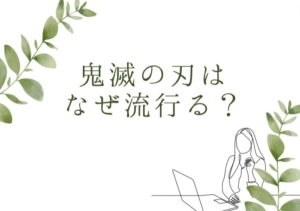
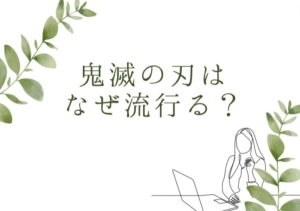
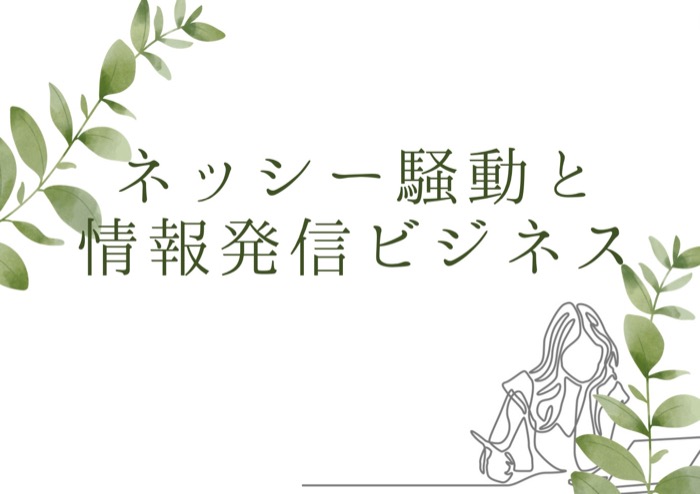
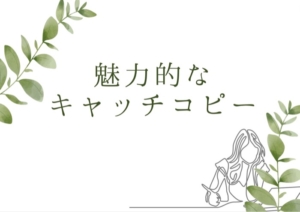




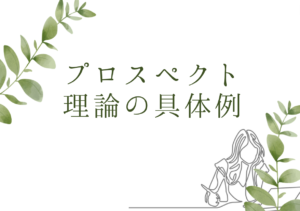
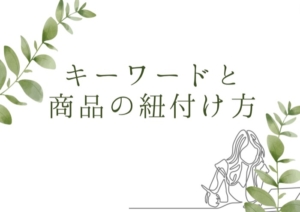
コメント